資産運用に興味を持ち始めたものの、「やっぱり資産運用はやめておいたほうがいいのだろうか?」と不安に感じていませんか。確かに、資産運用にはお金を増やすチャンスがある一方で、損をするリスクも存在します。本記事では、資産運用の基本的な仕組みやリスク、よくある失敗例を初心者向けに網羅的に解説します。メリットとデメリットを客観的に整理し、資産運用を始めるべきか迷っている方が自分なりの判断材料を持てるようになることが本記事の目的です。資産運用を「やめとけ」と言われる理由から、リスクとの向き合い方、始める前のチェックポイントまで詳しく見ていきましょう。
資産運用とは何か(仕組み)
まずは資産運用の基本について確認しましょう。資産運用とは、預金以外の方法で手持ちのお金を増やすために金融商品や実物資産に投資し、運用することを指します。単に銀行口座にお金を貯めておく「貯蓄」とは異なり、資産運用ではリスクを取ってリターン(利益)を狙う行為です。貯蓄は元本が保証される安心感がある一方で増えるスピードは緩やかですが、資産運用は元本保証がない代わりに工夫次第でより高い利回りを期待できます。
資産運用の代表的な手法には次のようなものがあります:
- 株式投資:企業の株を購入し、値上がり益や配当益を狙う。ハイリスク・ハイリターンの典型例で、市場や企業業績によって株価が上下します。
- 債券投資:国や企業の発行する債券を購入し、利息収入を得る。株式に比べリスクは低めですが、得られる利回りもやや低く安定的です。
- 投資信託:プロが運用するファンドに出資し、間接的に株式や債券などに投資する方法。少額から分散投資ができるので初心者にも利用しやすい商品が多いです。
- 不動産投資:アパートやマンションなど不動産を購入し、家賃収入や売却益を得る。まとまった資金が必要で流動性が低いものの、長期的な資産価値保持が期待できます。
- その他の資産運用:近年は金(ゴールド)や暗号資産(仮想通貨)への投資、FX(外国為替証拠金取引)なども個人で取り組めるようになっています。それぞれリスク・リターンの特性が異なります。
このように資産運用には多様な種類がありますが、共通する基本の仕組みは「一定のリスクを取って資産を増やすことを目指す」点です。反対に、銀行預金のようにリスクを極力取らずに資産を保全するのが貯蓄と言えるでしょう。どちらが良い悪いではなく、自分の状況に合わせて貯蓄と投資を使い分けることが大切だと金融庁も解説しています。
なぜ「資産運用はやめとけ」と言われるのか
資産運用に興味を持ち始めた人の中には、周囲から「資産運用なんてやめておけ」「素人が手を出すものじゃない」とネガティブな声をかけられた経験がある方もいるでしょう。では、なぜそのように言われるのでしょうか。主な理由や背景として、以下のポイントが挙げられます。
1. 元本割れなど損をするリスクへの不安
資産運用には損失(元本割れ)のリスクがつきものです。せっかく貯めたお金が減ってしまうかもしれない不安から、「リスクを取るくらいなら最初からやらない方がいい」という意見に繋がります。特に日本では長年にわたり預金重視の傾向が強く、2023年時点で日本の家計資産の50%超が現金・預金となっており、株式や投資信託への投資はわずか15%程度にとどまっています。半面、米国では家計資産の約51%が株式・投資信託で、現金・預金は13%ほどに過ぎません。
この違いは、日本ではリスクを取る資産運用になじみが薄く、不安を感じる人が多いことを示していると言えます。リスク=悪いものというイメージから、資産運用自体をギャンブルのように考えて敬遠する声もあります。
2. 短期間で大きく儲かるわけではない現実
資産運用に夢を見て「すぐにお金持ちになれるかも」と期待してしまう人もいます。しかし実際には、堅実な資産運用で短期間に資産を何倍にも増やすことはほとんど不可能です。
1年や2年で投資額が一攫千金的に増えるケースは稀で、コツコツと長い時間をかける必要があります。こうした現実を知らずに始めると期待外れに感じ、「そんなにすぐ増えないならやっても意味がない」「時間の無駄だ」という否定的な意見に変わってしまうことがあります。「短期で楽に儲けたい」という考えが強い人ほど、この現実とのギャップに失望しやすいでしょう。
3. 詐欺に遭う可能性への懸念
残念ながら、資産運用の世界には初心者を狙った投資詐欺も存在します。「必ず儲かる話がある」などと甘い勧誘を受けてお金をだまし取られたというニュースも後を絶ちません。実際に資産運用を装った詐欺は頻発しており、一見まともな会社を装うケースもあるため素人には見抜きにくいのが実情です。こうした話を聞くと「変な投資話に騙されるくらいなら最初から投資なんてしない方がいい」と思うのも無理はありません。
知識や経験が浅いうちは詐欺に遭うリスクが高いため、周囲が心配して「やめとけ」と忠告する場合もあります。
4. 知識不足だと失敗しやすい
資産運用はなんとなく始めてもうまくいくものではなく、正しい知識と計画が必要です。例えば、仕組みを理解せずにリスクの高い商品に手を出したり、市場の状況を読まずにタイミングを誤ったりすると、大きな損失につながりかねません。知識がないまま勘や他人の噂を頼りに運用してしまうと痛い目を見る可能性が高く、「勉強しない人は資産運用なんてしない方がいい」という指摘が出てきます。つまり金融リテラシー(お金の知識)の不足が、資産運用を敬遠すべきだとする意見の根底にあります。初心者自身も「難しそうで自分には無理かも」と萎縮してしまう理由の一つでしょう。
5. 投資には常にリスクが付きまとうという事実
どんなに安全そうな投資でもリスクはゼロになりません。投資先の企業が倒産したり、経済状況の変化で相場が急落したりすれば、投じたお金が目減りする危険性があります。また、銀行預金のように元本保証がされている金融商品はごくわずかで、大半の投資商品は元本割れの可能性があります。このため「絶対安心な運用法は無いのだからやめておけ」という慎重な声が上がるのです。特に元本保証のないことへの不安は大きく、リスクを取って増やすより減らさないことを優先したい人にとっては資産運用は勧められないと感じられます。
以上のような理由から、「資産運用はやめとけ(やめた方がいい)」という意見が存在します。しかし裏を返せば、これらの不安要素さえコントロールできれば資産運用で資産を着実に増やすことも可能です。大切なのはメリットとデメリットを正しく理解し、自分に合った方法で取り組むことだと言えるでしょう。
資産運用における失敗例
資産運用には失敗がつきものです。初心者の中には実際に運用を始めてみて損失を出し、「やっぱり資産運用なんてやめておけばよかった…」と後悔する人もいます。ここでは統計データに見る失敗の傾向や、初心者によくある誤解とその結果を紹介します。失敗例から学ぶことで、同じ過ちを繰り返さないようにしましょう。
資産運用で失敗した主な理由(アドバイザーナビ調査 2024年)。アンケートでは「知識不足」「冷静な判断ができなかった」が二大要因となっている。
上のグラフは2024年に行われた個人投資家へのアンケート結果です。**実に回答者の74.1%が「これまでに資産運用で損失を経験した」**と答えており、多くの人が何らかの失敗を味わっていることがわかります。
具体的な失敗談として多かったのは以下のようなケースです
ハイリスクな運用で大損してしまった
リスクの高い金融商品に一度に大金を投じてしまい、市場の変動で一気に資産を減らすケースです。例えばレバレッジを利かせたFX取引や、新興国株など値動きの大きい商品に深入りしすぎて大きな損失を被った、という声がありました。
周囲に勧められるまま投資して失敗した
知人やネット上の情報に影響され、「これが儲かるらしい」と聞いて深く考えずに飛び乗った結果失敗する例です。自分で十分調べずに他人任せで商品を購入すると、状況が変わった際に適切に対処できず損失につながります。
リスク管理をせずに投資して失敗した
損失が出たときにどう対処するか事前に決めていなかったり、資産配分のバランスを考えずに一点集中投資していたりするケースです。例えば株価が下がっているのに感情的になって損切り(損失を確定する売却)ができず、ずるずると含み損を拡大させてしまったという失敗談があります。
長期投資の商品を短期で手放してしまった
本来は長期運用でこそ効果が出るはずの商品を、目先の値下がりに焦って途中でやめてしまう例です。アンケートでも「長期保有が重要な投資信託が値下がりした際に焦り、積立を続けるべきところを全て売却してしまった」という苦い経験が報告されています。このように早まった解約やパニック売りは、後から振り返ると大きな機会損失や実損につながりやすい失敗パターンです。
「絶対儲かる」という話に飛びついてしまった
人間心理として、「楽に儲けたい」「チャンスを逃したくない」という気持ちから甘い話に乗ってしまうことがあります。例えば「○○という銘柄が確実に上がる」といった根拠薄弱な情報を信じ込んで投資した結果、大損してしまうケースです。詐欺までいかなくとも、いわゆるポンジスキーム的な高利回り商品や、ブームに沸いた暗号資産・ミーム株に遅れて飛び込んで暴落に巻き込まれるなど、「儲け話」に弱いと失敗しがちです。
初心者に共通する失敗例は、十分な知識や準備がないまま見切り発車してしまうこと
以上のような失敗例を見ると、初心者に共通しがちな誤りが浮かび上がってきます。それは「十分な知識や準備がないまま始めてしまうこと」「冷静さを欠いた判断をしてしまうこと」です。実際、先のアンケートでも失敗の原因として最も多く挙げられたのは「資産運用の知識が不足していた」(37.1%)、次いで「冷静な判断ができなかった」(34.3%)という結果でした。他にも「他人の意見に流されてしまった」「リスク管理ができていなかった」「投資先の分析をしていなかった」などが理由に挙げられており、準備不足や感情任せの行動が失敗につながっていることがわかります。
しかし、重要なのは失敗から学んで改善することです。アンケートによれば、失敗を経験した投資家の多くはその教訓から「長期・分散・積立投資を実行するようにした」(43.7%)、「投資の勉強をして知識を付けるようにした」(30.3%)といった対策を取っています。
一方、「これまで失敗したことがない」という投資家の過半数(51.2%)は「長期・分散・積立投資を心がけている」と回答しており、安全な運用を行うことが失敗防止の鍵だと述べています。
つまり、失敗しない人ほど基本に忠実な堅実運用を実践しているのです。
資産運用の失敗例から得られる教訓は明確です。「ハイリスクな近道」を狙うのではなく、「知識を身につけて長期的な視点で堅実に運用する」ことが成功への近道だということです。次章では、実際に資産運用のリスクとどう向き合っていけば良いか、基本的な考え方を解説します。
資産運用のリスクと向き合うには
資産運用を語る上で避けて通れないのがリスクとリターンの関係です。一般に「ハイリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターン」と言われるように、大きな利益を狙えばそれだけ損失の危険も高まり、リスクを抑えればリターンも小さくなる傾向があります。裏を返せば、極端に「損をしたくない」と思えば安全な預貯金に置くほかなくなり資産は増えにくく、「大儲けしたい」と欲をかけば無謀な賭けに出てしまい失敗する可能性が高まるということです。したがって資産運用では、自分にとって許容できるリスクの範囲(=リスク許容度)を見極め、その範囲内でリターンを追求することが大切です。
では具体的に、資産運用のリスクと上手に付き合うにはどうすればよいのでしょうか。基本的なポイントとして、金融庁やFP(ファイナンシャルプランナー)など専門家が強調する「長期・分散・積立」の考え方があります。
これらは資産運用の王道とも言えるリスクコントロール手法です:
長期投資
できるだけ長い期間運用を続けることです。時間を味方につけることで、利益の再投資による複利効果が大きくなり、安定した収益の確保が期待できます。短期的には相場の上下で損益がブレても、長期で持てば平均化されプラスに収束しやすくなるというメリットもあります。歴史的にも、株式市場などは長期では成長する傾向があり、長く持つほど損をするリスクが低減するというデータがあります。
積立投資(ドルコスト平均法)
一度にまとめて投資するのではなく、定期的に一定額ずつ投資していく手法です。毎月1万円ずつなど少額からコツコツ続けることで、価格が高い時には少なく、安い時には多く買うことになり、購入価格を平均化できます。これにより「高値掴み」や「安い時に買いそびれる」といったタイミングの失敗リスクを軽減できます。初心者でも無理なく始めやすい方法であり、アンケートでも失敗後に「投資信託をドルコスト平均法で積み立てるようにした」という声が多く聞かれました。
分散投資
一つの資産や銘柄に集中せず、複数の異なる資産に分散して投資することです。例えば国内株式だけでなく外国株式や債券、不動産投資信託(REIT)など値動きの異なる資産を組み合わせれば、一部の資産が不調でも他が補い全体の損失を抑えられます。分散の対象は「投資対象(株・債券・不動産など)」「地域(国内・海外)」「時間(購入タイミング=積立)」など多岐にわたります。特に初心者は、一つの商品に全財産を注ぎ込むようなことは避け、リスク分散を意識しましょう。
以上の長期・積立・分散を組み合わせることで、資産運用のリスクを大きく軽減し安定的な資産形成が期待できると金融庁も解説しています。
実際、先述のアンケートでも長期・分散・積立を心がけている投資家ほど失敗が少ないことが示されていました。
また、リスクと向き合う上でもう一つ大事なのはメンタル面のコントロールです。運用中は市場の変動で資産評価額が上下し、時にはマイナスになることもあります。その際に慌てて判断を誤らないようにするために、余裕資金で運用することとルールを決めておくことが有効です。生活費や緊急資金まで投資に回してしまうと、いざという時に取り崩さざるを得ず損失確定してしまったり、日々の値動きに一喜一憂して冷静さを欠いたりしがちです。アンケート結果でも「余剰資金で運用していなかった」ことを失敗理由に挙げた人が一定数いました。したがって、当面使う予定のない余裕資金で行うことが鉄則です。また、「〇%下落したら損切りする」「〇年は売却しない」など自分なりのルールを決め、それに従うことで感情に流されない投資判断を下せます。実際に、失敗していない投資家ほど「事前に投資先をしっかり分析する」「常に冷静に判断する」など計画的・冷静な姿勢を持っているとのデータもあります。
まとめると、資産運用のリスクと向き合うには「知識を身につけ、長期・分散・積立で堅実に運用し、余裕資金で計画的に行う」ことがポイントです。こうした基本を守れば、リスクを抑えつつリターンを積み重ねていくことが十分可能になります。完全にリスクを無くすことはできませんが、コントロールすることはできるのです。
資産運用をおすすめしない人の特徴
ここまで資産運用のメリット・デメリットやリスク対策について説明してきましたが、とはいえ誰にでも資産運用が必ずしも適しているわけではありません。人によっては無理に資産運用をせず、預貯金など他の方法で資産管理した方が良い場合もあります。一般に、以下のような特徴に当てはまる人は資産運用をおすすめしない傾向があります。
リスク許容度が極めて低い人
お金が少しでも減る可能性に耐えられない人は、たとえ少額の含み損でも大きなストレスを感じてしまいます。資産運用には価格変動がつきものなので、リスクに対する不安が極度に強い場合は無理に投資をするとかえって精神的に疲弊し、適切な判断ができなくなる恐れがあります。元本割れのリスクを一切取りたくないなら、無理に資産運用をせず預金や安全な貯蓄型保険などに留めておく方が安心でしょう。
短期的な利益を過度に期待している人
「すぐにでもお金を増やしたい」「来月までに◯◯万円欲しい」といった短期志向が強い人も、資産運用には向きません。前述の通り、堅実な資産運用は短期で大儲けできるものではなく、時間をかけて増やすものです。短期で結果を求める人は、じれったくなってリスクの高い手段に飛びついたり、少し損しただけで投げ出したりしがちです。一攫千金を夢見るタイプの人は、投資ではなく宝くじやギャンブルに走ってしまうケースもありますが、それでは本末転倒です。短期の期待が大きすぎる人は、まず長期目線の重要性を理解しないと資産運用はうまくいかないでしょう。
継続的に勉強する意思のない人
資産運用は始めたら終わりではなく、継続的な情報収集や学習が欠かせません。経済の状況は刻々と変化しますし、新しい金融商品や制度も登場します。そういった変化にまったく興味がなく「勉強するのは面倒だ」という人は、適切な運用判断ができずに不利な商品を選んでしまったり、状況の変化に対応できなかったりする恐れがあります。金融リテラシーは一朝一夕には身につきませんが、少しずつでも学ぶ姿勢がないと、結局他人任せの運用になって失敗する可能性が高まります。勉強嫌いで放置してしまう人には資産運用はおすすめできません。
以上の特徴に心当たりがある方は、無理に資産運用を始めなくても良いかもしれません。特に、少しのマイナスも我慢できない人や「楽して儲けたい」願望が強い人**は、資産運用に向いていない可能性が高いです。一方で、「リスクは怖いけど少しずつ慣れていきたい」「勉強しながら挑戦したい」という気持ちがあるなら、工夫次第で資産運用を取り入れることも可能です。次章では、資産運用を始めるか迷っている人に向けて、実際に始める前に確認すべきポイントやアドバイスをお伝えします。
資産運用を始めるか迷っている人へのアドバイス
資産運用に興味はあるものの、不安もあって踏み出せずにいるという方に向けて、最後にいくつか意思決定のヒントを提示します。始める・始めないを判断する際には、次のポイントを自問してみてください。
1. 自分の目的・価値観を明確にする
まずはなぜ資産運用をしたいのか、その目的や自分の価値観をはっきりさせましょう。老後資金を準備したいのか、将来の住宅購入や教育資金を作りたいのか、それとも単にお金を増やして経済的余裕を持ちたいのか――人それぞれ目的は違います。目的によって適した運用手法やリスク許容度も変わってきます。例えば、「老後までに時間をかけて増やしたい」のなら長期分散投資が向いていますし、「数年内に使う予定の資金を増やしたい」のなら安全資産中心で大きなリスクは取らない方が良いかもしれません。また、自分の性格も考慮しましょう。リスクでドキドキするのが耐えられない性格なのか、それとも多少の変動は許容できるのか。資産運用は手段であって目的ではないことを念頭に、自分の人生設計に照らして必要性を考えてみてください。「なぜ増やしたいのか」「どのくらいの期間でどれだけ増やしたいのか」を明確化することで、資産運用をすべきか否か、自ずと判断しやすくなります。
2. 少額・低リスクから試してみる
迷っているなら、いきなり大金を投じる必要はありません。まずは少額から、できるだけ低リスクな方法で資産運用を試してみるのも一つの手です。例えば毎月数千円程度から始められる投資信託の積立や、元本保証ではないものの値動きの小さい債券型のファンドなどを購入してみるとよいでしょう。最近では100円単位で投資信託を積み立てられるサービスや、株式も1株から買える制度も整っています。「授業料」だと思って少額で市場に参加してみることで、実際の値動きを体感しながら学ぶことができます。仮に少額で損失が出ても痛手は小さくて済みますし、得られる経験値は貴重です。また、投資のシミュレーションができるゲームやアプリもあるので、仮想体験で感覚を掴むのも良いでしょう。「百聞は一見にしかず」で、実際に少しでも運用してみると、書籍やネットで勉強するだけでは得られない洞察が生まれます。小さく始めて様子を見ることで、自分に資産運用が向いていそうか見極めることができます。
3. 学びながら進める姿勢を持つ
資産運用を始めるからには、常に学び続ける姿勢を大切にしましょう。初心者は誰でも最初は分からないことだらけです。最初から完璧な知識を求める必要はありません。重要なのは、実践しながら知識と経験を積み重ねていくことです。
具体的には、本やウェブサイトで投資の基礎を勉強したり、信頼できる公的機関(例えば金融庁のウェブサイトや日本FP協会のコラム)で正しい情報を得たりしましょう。最近は初心者向けのセミナーやオンライン講座、無料相談窓口なども充実しています。そうしたリソースを活用し、疑問点を解消しながら進めると安心です。運用を続けていると経済ニュースにも自然と関心が向くようになり、知識が深まっていきます。
大切なのは、失敗からも学ぶ前向きな姿勢です。一度の損失で投げ出すのではなく、「なぜ失敗したのか」「次はどうすればいいか」を考え、次の運用に活かしていきましょう。学習と実践を繰り返せば、初心者から一歩ずつ成長し、いずれ自信を持って資産運用に取り組めるようになるはずです。
以上のポイントを踏まえてもなお「やはり自分には難しそうだ」と感じるなら、無理に始める必要はありません。逆に「少し不安はあるけどチャレンジしてみたい」という前向きな気持ちが芽生えたなら、まずはできる範囲でスタートしてみる価値はあります。重要なのは、周囲の声に流されるのではなく自分自身の意思と判断で決めることです。
まとめ
「資産運用はやめておいたほうがいいのか?」という疑問に答える形で、資産運用の仕組みやリスク、失敗例、そして向き合い方について解説してきました。確かに資産運用には元本割れのリスクもありますし、初心者が陥りがちな失敗パターンも存在します。短期的に見ればマイナスになる局面もあり、不安になる気持ちも理解できます。そのため「やめとけ」という意見が出るのも一理あります。
しかし一方で、資産運用は将来に向けてお金に働いてもらう有効な手段でもあります。正しい知識を身につけ、長期的な視点でコツコツと続ければ、預貯金よりも効率よく資産を増やせる可能性があります。事実、長期・分散・積立といった基本に忠実に運用している人ほど失敗が少なく、着実に資産形成を行っているというデータも示されています。
要は使い方次第なのです。
資産運用をするかしないかに絶対的な正解はありません。大切なのは、本記事で述べたようなメリット・デメリットを踏まえて、自身の判断軸で決めることです。他人に勧められたからとか、皆がやっているからといった理由ではなく、自分の目的やリスク許容度に照らして「自分はどうすべきか」を考えてみてください。その上で、やると決めたならばルールを守って慎重に取り組み、やらないと決めたならば無理に流行に乗らない勇気も必要です。
資産運用は怖いものでも特別なものでもなく、正しい知識と適切なスタンスがあれば人生の目標を支える強力な味方になり得ます。一方で準備不足で臨めば手痛い失敗にも繋がります。本記事の内容が皆さんの判断材料となり、今後のお金の付き合い方を考える一助となれば幸いです。最後に強調したいのは、情報に踊らされず自分の頭で判断することの大切さです。資産運用をするにせよしないにせよ、「自分の軸」を持って決断し、行動していきましょう。そうすれば、どのような選択をしたとしても後悔のない健全なお金との付き合い方ができるはずです
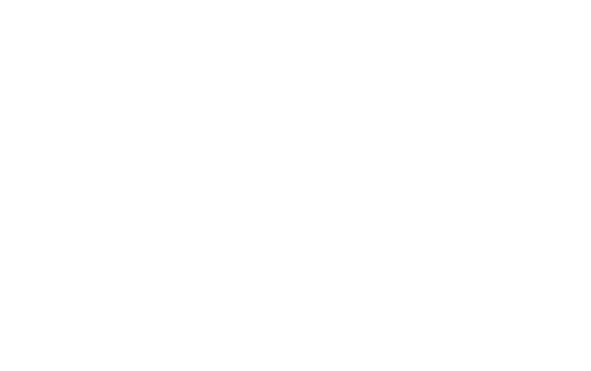 資産運用ノート
資産運用ノート 