資産運用の世界でしばしば耳にする「ヘッジファンド」という言葉。しかし、「ヘッジファンドはおすすめしない」といった声も多く、特に投資初心者にとってはその実態やリスクが分かりにくいものです。本記事では、約200万円の投資を検討する初心者を主な想定読者として、ヘッジファンドの基本から「おすすめしない」と言われる理由、一般投資家にとっての課題、そして例外的に有効なケースや代替となる投資手段までを包括的に解説します。金融庁やモーニングスター等の信頼性の高い情報源から得られたデータを引用しながら、初心者でも理解しやすいようフォーマルな口調で整理しました。
ヘッジファンドとは?基本的な仕組みと特徴
ヘッジファンドとは、伝統的な投資信託(ミューチュアル・ファンド)などとは異なり、様々な取引手法(空売り・レバレッジ・デリバティブ取引など)を駆使して、市場が上昇局面でも下落局面でも利益を追求することを目的としたファンドです。
名前の由来は「hedge(ヘッジ=リスク回避)」にあり、相場の上げ下げ双方に賭けることで市場変動にかかわらず絶対的な収益を目指す点に特徴があります。
ヘッジファンドは通常、私募形式で資金を集め、少数の裕福な投資家や機関投資家を対象に運用されます。法律上は公募の投資信託のように一般大衆に広く販売されるものではなく、金融商品取引法の規制下でも適格投資家向けの商品として位置づけられています(無登録業者が一般に勧誘することは違法です)。
一方、伝統的な投資信託は数百円~数万円程度から小口で購入可能で、証券会社や銀行を通じ誰でも買える公開商品です。
ヘッジファンドと伝統的な公募投資信託(例えばインデックスファンド)との主な違いをまとめると以下のようになります。
| 項目 | ヘッジファンド (私募ファンド) | 公募投資信託・ETF (インデックス型等) |
|---|---|---|
| 運用手法 | 制約が少なく自由(空売り・レバレッジ・デリバティブ等) | 規制範囲内で限定的(株式・債券など伝統資産が中心) |
| 目標 | 絶対収益の追求(市場環境に左右されにくい利益) | 相対収益の追求(指数やベンチマークに連動・上回る) |
| 情報開示 | 限定的(一般公開義務なし、投資家向けレポートのみ) | 高い(目論見書や運用報告書を通じ定期的に情報開示) |
| 手数料 | 2%+成功報酬20%(典型的な「2と20」モデル) | 信託報酬0.1~1%程度(成功報酬なし) |
| 最低投資額 | 数百万円~数千万円が必要(例:最低1000万円) | 数百円から購入可能(少額積立にも対応) |
| 流動性 | 低い(解約は年数回など制限あり) | 高い(基本毎日換金可、上場ETFなら市場で即売買可) |
| 主な投資家 | 富裕層・機関投資家(年金基金、金融機関など) | 個人投資家一般・機関投資家(誰でも参加可能) |
| 国内外の違い | 国内運用会社もあるが規模小(多くは海外拠点で運用) | 国内外問わず様々(海外ETF含め一般投資家が購入可) |
| 監督・規制 | 金融庁による届出・登録(第二種金融商品取引業など) | 金融庁登録の運用会社による厳格な規制下 |
このように、ヘッジファンドは運用手法の自由度や対象投資家の範囲において、公募の投資信託とは大きく異なります。
国内にもヘッジファンド運用会社は存在するものの、その多くは海外籍ファンドを日本の投資家に紹介する「ファンド・オブ・ファンズ」形式や、海外拠点で運用を行うケースが一般的です。日本市場に特化したヘッジファンドの残高はリーマンショック前の2006年4月に約390億ドルまで拡大した後、大幅に縮小し、2012年時点では約160億ドル(約2兆円)程度とピーク時の半分以下になっていました。
一方でアメリカやヨーロッパには数兆ドル規模の巨大ヘッジファンド産業が存在し、世界全体のヘッジファンド資産規模は約3兆ドルと言われています。
「ヘッジファンドはおすすめしない」と言われる主な理由
では、なぜヘッジファンドは個人投資家には「おすすめできない」と言われるのでしょうか。その主な理由(デメリット)として、一般に以下の5つが挙げられています
情報が少なく不透明
ヘッジファンドは非公開型のファンドであり、一般の投資信託のように詳細な運用情報を公表する義務がありません。運用成績やポートフォリオの内容は基本的に投資家だけに限定開示され、第三者が評価する指標(例えばモーニングスターの星評価のようなもの)もありません。そのため、外部からは実態を把握しづらく、「よく分からないものに大金を預ける」ことになりがちです。この情報の非透明性ゆえに、投資初心者には判断が難しくリスクが見えにくい点がデメリットです。
最低投資額が高額
多くのヘッジファンドは最低出資額が数百万~数千万円と高額に設定されています。日本では最低1000万円以上という例も一般的で、そもそも富裕層でなければ投資の土俵に立てません。200万円程度の資金しかない初心者が直接ヘッジファンドにアクセスするのは現実的に困難です。また最低額ぎりぎりで参加した場合でも、その資金を長期間拘束されるリスクがあります。いずれにせよ、投資資金の大半を一つのファンドに預けることになるため分散が利かず、初心者には適しません。
手数料が非常に高い
ヘッジファンドの手数料体系は「2-20」と呼ばれるように年率2%の管理報酬+運用益の20%の成功報酬が典型です。例えば年間10%の利益を上げても、2%は固定手数料で差し引かれ、残り8%のうち20%(=1.6%)が成功報酬として取られるため、投資家の手取りは約6.4%に目減りします。
運用成績がマイナスの場合は成功報酬は発生しないとはいえ、それでも2%程度の基本手数料は差し引かれます。他方、一般的なインデックスファンドの信託報酬は年0.1~0.3%程度、アクティブ型の投資信託でも1~2%程度が上限で成功報酬はありません。したがってヘッジファンドは他の投資商品に比べ圧倒的にコスト負担が重いです。
高い利益目標を掲げるヘッジファンドですが、高コストゆえに投資家の取り分が減り、実質リターンが平凡になることもしばしば指摘されています(この点については後述する実績データでも詳しく触れます)。
実際、全米最大の年金基金であるカリフォルニア州職員退職年金基金(カルパース)は「ヘッジファンドは手数料が高すぎ複雑すぎる」と結論づけ、2014年にヘッジファンド投資から資金を引き上げています。カルパースに追随して多くの大学基金や保険会社もヘッジファンド投資を縮小し、業界ではファンド閉鎖が相次ぎました。このようにプロの機関投資家でさえ敬遠する高コスト構造は、個人が安易に手を出せるものではありません。
詐欺・トラブルのリスク
ヘッジファンドという仕組み自体は合法ですが、その閉鎖性ゆえに悪徳業者が紛れ込む余地もあります。実際に過去には世界最大級のポンジ・スキーム(ねずみ講的詐欺)事件とされるバーナード・マドフの事件(被害総額650億ドル規模)が起きており、「ヘッジファンド=怪しい」とのイメージを植え付けました。日本でも2012年にAIJ投資顧問事件(企業年金約2000億円の巨額損失隠し)が発覚し、金融庁が業務停止処分を下す事態となっています。
これは厳密には企業年金向けの投資顧問会社による不正でしたが、「高利回りをうたうファンド」による事件としてヘッジファンド同様のリスクを印象付けました。また、無登録業者が「海外ヘッジファンドへの投資話」を持ちかけて資金を騙し取るようなケースも報告されています。
金融庁も注意喚起しており、「絶対にもうかる」「元本保証」といった勧誘文句は典型的な違法行為(断定的判断の提供や損失補填の約束)として挙げられています。このように詐欺的な案件に巻き込まれるリスクが否めない点も、「初心者にはおすすめできない」と言われる所以です。
流動性が低く換金しづらい
ヘッジファンドは中途解約に制限がある場合が多く、投資してから半年~1年は引き出し禁止(ロックアップ期間)が設定されることも一般的です。解約できる場合でも年に1~4回程度の受渡日しかなく、それ以外のタイミングで現金化することは困難です。
一方で公募投資信託であれば毎日基準価額が算出されいつでも解約可能、ETFなら市場でリアルタイムに売買できます。ヘッジファンドでは突然資金が必要になった際に引き出せないリスク(流動性リスク)が高く、これは特に資金規模の小さい個人投資家にとって致命的な欠点となりえます。
また、金融危機時には解約希望が殺到してファンド側が「ゲート(解約制限)」を発動し、投資家が資金を引き出せなくなる例も過去にありました。したがって、流動性ニーズの高い人や予期せぬ出費に備えたい人には不向きと言えます。
以上のような理由から、ヘッジファンドは一般の個人投資家、特に経験の浅い初心者にはリスクが高くメリットが見合わないとされています。もちろん、全てのヘッジファンドが危険というわけではなく、中には優秀な運用成績を長年維持しているファンドも存在します。
しかしそのようなファンドは極めて数少なく、また縁故や専門家の紹介なしには投資機会自体にアクセスできないことがほとんどです。
デメリットの大きさと参入障壁の高さを踏まえると、「万人におすすめできる投資先ではない」というのが大方の専門家の見解です。
ヘッジファンドの実際のリターンと一般投資家にとってのハードル
「高リスクだが高リターンを狙える」と言われるヘッジファンドですが、実際の運用成績(リターン)はどうなのか、データで確認してみましょう。また、一般投資家が直面するアクセス上のハードルについても掘り下げます。
平均的な成績:市場平均に劣後?
平均的なヘッジファンドの年間リターン(オレンジ線)は、2011~2020年のすべての年で主要株価指数(S&P500指数、青線)のリターンを下回りました。
2011年から2020年の10年間を通算すると、ヘッジファンドの年平均利回りは約5.0%で、S&P500指数の年平均14.4%を大きく下回っていたとの分析もあります。
特に株式市場が好調な年にはその差が顕著で、例えば2013年はヘッジファンド平均+10%程度に対しS&P500は+30%、2019年もヘッジファンド+10%前後に対しS&P500は+28%と大幅に負け越しています。
一方、株式市場がマイナスとなった年(例えば2018年)にはヘッジファンドの下落幅がやや小さくなっていますが、それでも「損失を完全にヘッジする」ほどの効果は出せていないことが分かります。実際、「ヘッジファンド」という名前から連想されるような下落相場での抜群の守備力は、平均的に見れば発揮されておらず、ゼロ近辺のリターンにとどまるのがせいぜいです(2018年はS&P500が-4%程度、ヘッジファンド指数がほぼ±0%でした)。
このように、ヘッジファンド全体の平均では市場指数を下回る低調な成績しか残せていないという実態があります。
もちろん、中には市場を大きく上回るリターンを叩き出した優秀なヘッジファンドも存在します。しかし、それはごく一部であり、生存バイアス(成績不振のファンドは途中で消滅する)も考慮すると、事前に勝ち組ファンドを選び出すのは極めて難しいとされています。「オルタナティブ投資の神秘性」がもてはやされた2000年代前半には、ヘッジファンド全体でも年率+15%近い高リターンを挙げていた時期がありましたが、近年(2010年代以降)は平均+5%前後に低下し、主要な債券指数の利回りにも劣後する状況です。
実際、日本のニッセイ基礎研究所の分析でも、2005~2014年のヘッジファンド平均年率リターン+7.9%が、直近5年(2015~2019年)には+3.9%に低下したと報告されています。
つまり、ヘッジファンドの収益力は過去数十年で大きく低下傾向にあるのです。
この背景には、ヘッジファンド業界の過当競争と市場環境の変化が指摘されています。ファンドの数が増えすぎた結果、かつて有効だった裁定取引のチャンスが収縮し、ゼロ金利下で株式市場が急伸する中で相対的魅力が薄れたことなどが原因とされています。
さらに先述の高額な手数料もパフォーマンス低迷の一因です。著名投資家ウォーレン・バフェット氏はヘッジファンドの高コスト体質を一貫して批判しており、2008年には「ヘッジファンドの10年成績は市場平均に勝てない」という賭けを提案しました。
結果は周知の通り、S&P500に連動するインデックスファンドが10年で+125.8%のリターンを上げたのに対し、ヘッジファンドの詰め合わせは+36%にとどまり、見事バフェット氏が勝利を収めたと報じられています。
バフェット氏はこの結果を受けて「高額なフィーと凡庸な運用者によってヘッジファンドの成績は冴えなかった」と指摘し、ヘッジファンドに巨額の報酬を支払う価値に疑問を呈しました。
以上のデータから言えることは、「平均的なヘッジファンドのリターンは、決して夢のように高いものではなく、むしろシンプルな株式指数投資に負けている」という現実です。
したがって、「ヘッジファンド=ハイリスクだがハイリターンが期待できるから挑戦する価値がある」と単純には考えないほうが良いでしょう。
リスクに見合うだけのリターンを得られていない可能性が高いからです。
一般投資家にとってのアクセス障壁
ヘッジファンドの成績面での魅力が必ずしも高くないことに加え、一般投資家が投資する際のハードルの高さも見逃せません。既に述べたように、多くのヘッジファンドは最低投資額が極めて高く設定されており、日本国内で販売される海外ヘッジファンドでも「一口1000万円」「最低5000万円以上」などの条件が付くケースがあります。
したがって、数百万円程度の資金しかない個人が直接参加することはほぼ不可能です。
「それならば少額から参加できるヘッジファンドはないのか?」と思われるかもしれませんが、基本的にありません。
一部にはファンド・オブ・ヘッジファンズ(複数のヘッジファンドに分散投資する投資信託)が公募投信や海外ETFとして存在するものの、それらも追加で手数料が上乗せ(通常の信託報酬+成功報酬)されるため、コスト負担はさらに重くなります。また、期待通りの分散効果やリターンが得られず低迷する商品も多く、近年はあまり人気がありません。
さらに、仮に資金面のハードルをクリアできたとしても、前述の情報開示の少なさや流動性の低さから生じる不安は付きまといます。プロの投資家であればファンド運営者との個別面談で詳細情報を得たり、専門のアドバイザーを雇ってデューデリジェンス(ファンド調査)を行ったりできますが、個人がそこまで行うのは困難です。自分では中身を十分理解できない金融商品に大金をロックされるという状況は、精神衛生上も好ましくありません。
総じて言えば、ヘッジファンドは「縁故と資金力のある一部の投資家」だけが参加できる閉鎖的なクラブのような存在であり、そうしたコミュニティに属さない一般の個人投資家には 縁遠い投資先 です。無理に門戸を叩こうとしても、高額な手数料でパフォーマンスを毀損され、身動きの取れないまま市場平均以下の成績に甘んじるリスクが高いでしょう。
以上の観点から、ヘッジファンドは初心者どころか多くの個人投資家にとって非現実的かつ非効率な選択であり、「おすすめしない」と結論づけられるのです。
ヘッジファンドを有効活用できるケースはあるか?
ここまでヘッジファンドのデメリットを中心に述べてきましたが、ではどんな場合にヘッジファンドが有効となりうるのか、例外的なケースも考えてみましょう。
結論から言うと、ヘッジファンドを活用できるのは主に超富裕層や機関投資家など、潤沢な資金と高度な運用ニーズを持つ投資家層です。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
大型ポートフォリオの一部として分散投資に組み入れる場合
何百億円もの資産を運用する富裕層や機関投資家にとって、株式・債券など伝統的資産だけではリスク分散が十分でない場合があります。ヘッジファンドはその低相関の投資戦略により、既存ポートフォリオと異なる値動きをすることが期待できます。例えば株式市場が低迷する局面でも特定のヘッジファンド戦略(マーケットニュートラルやグローバルマクロなど)はプラスの収益を出す可能性があり、全体として損失を和らげる効果が見込めます。実際、日本の企業年金基金でも平均して5%前後をヘッジファンドに配分しているとのデータがあり、分散投資の一環としてヘッジファンドを位置付ける例は存在します。特に海外の大学基金(例:イェール大学の基金)などはポートフォリオの二桁%をヘッジファンドなどオルタナティブ資産に振り向けていることで有名です。
高度な投資ニーズ(オルタナティブ戦略)を求める場合
伝統資産では得られないユニークなリターン源泉を求めて、あえてヘッジファンドを活用するケースもあります。例えば、ある富裕層投資家が「株式や債券とは無関係に動く絶対収益型の商品」を欲している場合、商品先物に特化したCTA戦略や、裁定取引に徹したマーケットニュートラル戦略のヘッジファンドに投資することで、そのニーズを満たすことができます。こうした戦略は一般の公募商品では手に入りにくく、ヘッジファンドならではの強みです。また、近年ではAI(人工知能)やビッグデータ解析を駆使したヘッジファンドも登場しており、最新テクノロジーによる運用手法をポートフォリオに取り入れたいと考える先進的な投資家には魅力的に映るでしょう。
資産規模が大きく長期視点で運用できる場合
ヘッジファンド投資は前述のように流動性が低く、短期的な出入りには向きません。裏を返せば、当面使う予定のない資金を長期で預けておける超長期志向の投資家であれば、その間のマーケットサイクルを超越した絶対収益追求が可能になります。超富裕層であれば全資産の数%をヘッジファンドに配分しても生活に支障はなく、10年単位で気長に運用を任せることができます。例えば世界的富豪ファミリーの中には、信頼するヘッジファンドマネージャーに何十年も資産を託し続けているケースもあります。このように時間と資金の余裕がある投資家にとっては、ヘッジファンドも有力な選択肢となりえます。
ヘッジファンドを「ポートフォリオ全体の中の一要素」として適切にコントロールできるならおすすめ
以上のケースに共通するのは、ヘッジファンドを「ポートフォリオ全体の中の一要素」として位置付け、適切にコントロールできることです。決してヘッジファンド単体に全財産を賭けるのではなく、豊富な資産の一部を割り当てることではじめてメリットが発揮されます。極端な例を言えば、100億円持つ投資家が5億円をヘッジファンドに投じてリスク調整後リターンを0.1%引き上げる、といった世界です。それほどの規模や余裕がない場合、無理にヘッジファンドを使わずとも通常の資産配分で十分と言えるでしょう。
ヘッジファンドをやめた方がいい人の特徴
上記を踏まえ、ヘッジファンド投資に向かない人(やめておいた方がよい人)の特徴を整理します。以下に当てはまる場合は、ヘッジファンド以外の代替案を検討するのが賢明です。
投資経験が浅い初心者
ヘッジファンドは仕組みが複雑で情報も限られるため、経験豊富な投資家向けの商品です。投資を始めたばかりの初心者が理解しないまま手を出すと、想定外のリスクに晒される恐れがあります。初心者はまず基本的な資産運用(預金・債券・株式・投資信託など)の経験を積み、リスクとリターンの関係を実感することが先決でしょう。
少額資産しかない人
先述のようにヘッジファンドは富裕層向けの商品であり、数百万円~数千万円程度の資産しかない人にはそもそも門戸が開かれていません。仮に最低額ギリギリで参加できるとしても、ポートフォリオの大部分を占めてしまい分散投資になりません。資産規模が小さいうちは、まず低コストで分散の利いた商品のみに絞るのが定石です。
流動性を重視する人(近い将来資金が必要になる可能性がある人)
住宅購入や教育資金、緊急予備資金など、数年以内にまとまったお金が必要となる予定がある人にはヘッジファンドは不向きです。ロックアップ期間や解約制限で自由に現金化できない可能性があるため、必要なときに資金を取り出せないリスクがあります。そうした人は代わりに流動性の高い上場ETFや短期債ファンドなどを用いるべきです。
「絶対に儲かる」といった甘言を信じてしまいがちな人
ヘッジファンドに限らず、高利回り商品には詐欺的案件が紛れることがあります。リスクを正しく認識せず「自分だけは大丈夫」と思い込んでしまう人は最も危険です。ヘッジファンドの勧誘で「安全に年利○%保証」などと言われたらまず詐欺を疑うべきであり、そういった誘惑に流されやすい人は最初から近寄らない方が賢明です。
以上に該当する場合、ヘッジファンドという選択肢自体を一旦脇に置き、代替となる現実的な投資先に目を向けましょう。では、具体的にどのような代替手段があるでしょうか。
初心者向けの代替投資先:長期・分散・低コストの商品を
ヘッジファンドに投資しない場合、代わりに検討すべき代表的な投資先として以下が挙げられます。
インデックスファンド・ETF(上場投資信託)
最もオーソドックスで推奨されるのが、低コストで市場全体に分散投資できるインデックスファンドやETFです。例えば、日経平均やS&P500、全世界株式指数などに連動する投資信託やETFに積立投資すれば、長期的に年平均5~7%程度のリターンが期待できます。実際、米国株式の代表であるS&P500指数は過去約100年の平均年率リターンが約10%と言われています。
ヘッジファンド平均を上回るこの水準のリターンを、誰でも手軽に低コストで享受できるのがインデックス投資の強みです。日本の金融庁も長期・積立・分散投資の重要性を提唱しており、こうしたインデックス型商品は「長期の投資に適した本来あるべき商品」と位置付けられています。NISA(少額投資非課税制度)なども活用し、まずはこれら王道商品で資産形成を始めるのが良いでしょう。
アクティブ型投資信託(公募ファンド)
もし「市場平均以上のリターンを狙いたい」という希望がある場合は、実績のあるアクティブ運用の投資信託を検討する手もあります。ヘッジファンドほどではありませんが、中には独自の戦略でベンチマークを上回る成果を上げている投資信託も存在します。モーニングスター社のファンドアワードなどで表彰されているような優秀ファンドを選べば、年率10%近い成績を残している例もあります。ただし、アクティブファンドは手数料が高め(信託報酬1~2%程度)で、常に市場に勝てる保証はありません。ヘッジファンドよりは透明性・流動性が高いとはいえ、基本はインデックス投資の補完と考え、資産の一部でチャレンジするぐらいが適切です。
債券・リート(不動産投資信託)など他の資産クラス
ヘッジファンドで分散効果を狙う代わりに、債券やリートといった資産クラスに分散するのも王道の手法です。例えば株式と債券は一般に逆相関傾向があるため、両方を組み合わせればポートフォリオ全体の値動きが安定します。近年は低金利でしたが、金利上昇局面では債券投資の妙味も増します。またJ-REITやグローバルREITなど不動産投資信託は、株式とは異なる高配当利回り資産として人気があります。これら伝統的資産であれば情報開示も十分で流動性も高く、初心者でも扱いやすいでしょう。ヘッジファンドに頼らずとも、基本的な資産配分(例:株50%・債券50%など)でかなりの分散効果が得られることは、金融庁のシミュレーション等でも示されています。
ロボアドバイザーなどおまかせ運用サービス
もし自分で商品を選ぶのが難しい場合は、ロボアドバイザー(AI搭載の自動運用サービス)を利用する手もあります。ロボアド各社は利用者のリスク許容度に応じて株式・債券・リート等に分散投資するポートフォリオを提案し、自動でリバランスまで行ってくれます。手数料は年0.5~1%程度かかりますが、ヘッジファンドの2%+成功報酬に比べればはるかに低コストです。特に投資初心者で「何から手を付けていいか分からない」場合、まずはロボアドで数十万円から運用を始め、感覚を掴むのも一つの方法でしょう。ロボアドは金融庁の登録業者が提供しており、預けた資産も分別管理されるため安全性も高いです。
以上のように、代替手段はいくらでも存在し、その多くはヘッジファンドより低コスト・低リスク・高流動性です。特にインデックスファンドやETFは**「ほったらかし」で市場平均のリターンを享受できる**点で、忙しい社会人や投資に時間を割けない人にも適しています。実際、「ヘッジファンドに投資するくらいなら、自分で何もしないでインデックスファンドに投資した方がマシだ」という趣旨の指摘も専門家からなされます。
まさに、「You can beat the pros by doing basically nothing(何もしなくてもプロに勝てる)」というわけです。
まとめ:ヘッジファンドは慎重に見極め、まずは王道の資産運用から
ヘッジファンドは一見すると魅力的なキーワード(プロが運用/市場に左右されない高収益追求など)が並びますが、その実態は高額な手数料と高いハードル、そして必ずしも高くない平均リターンであることが分かりました。特に資産運用の初心者や少額資産の投資家にとって、ヘッジファンドは基本的におすすめできない選択肢です。「ヘッジファンドで一発当てたい」といった誘惑は捨て、まずは長期・積立・分散による堅実な運用で着実に資産形成を図るのが遠回りなようでいて最善の道と言えるでしょう。
ただし、本記事で述べた内容はあくまで一般論です。世の中にはごく少数ですが素晴らしいヘッジファンドも存在し、それに早くから投資して巨額の富を築いた人もいます。しかしそれは宝くじ的な当たり外れの世界であり、再現性のある手法ではありません。多くの人にとって現実的なのは、金融庁も推奨するような「長期・積立・分散」の地道な投資**であり、その中にヘッジファンドが占める必要不可欠な役割は見当たらないのが実情です。
むしろ、本記事で見てきたように機関投資家ですらヘッジファンドを敬遠する動きがあること、平均パフォーマンスが市場平均を下回っていることを踏まえれば、無理に背伸びして手を出す理由は乏しいでしょう。
今後投資経験を積み、ご自身の資産が大きく増え、なおかつ「それでもヘッジファンドでなければ達成できない投資目標」が明確になったときに、初めて専門家の助言を得ながら検討すれば良いのです。それまでは、足元の堅実な資産運用に注力することを強くおすすめします。
参考文献・出典:ヘッジファンドの定義および特徴(第二種金融商品取引業協会WEBサイト)t2fifa.or.jp、海外機関投資家のヘッジファンド離れ(Bloomberg)about.bloomberg.co.jp
、ヘッジファンド平均リターンと株式指数の比較(Reuters・Bloomberg)nasdaq.com,jp.reuters.com、AIJ投資顧問事件(Reuters)reuters.com、ウォーレン・バフェット氏の発言(Bloomberg)bloomberg.co.jp
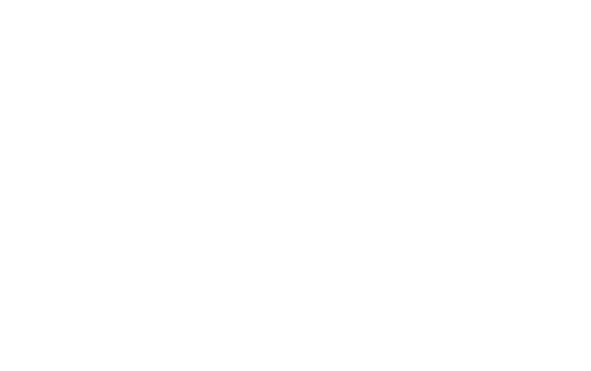 資産運用ノート
資産運用ノート 